column ココロの特集
失敗を怖がる子どもに親ができること|つまずきを成長につなげるサポート術

「失敗したらどうしよう……」
「間違えたら友達に笑われるかも?」
新しいことに挑戦したり、人前で発表したりする場面で、そんな不安を感じる子どもは少なくありません。しかし、親や教師から「間違ってもいいよ」といわれることで安心したり、失敗を気にせずのびのびと振るまえるようになったりすることもあります。「間違えてもいい」「失敗も大切」と親や周囲が認識することの重要性、そして、子どもの「失敗から学ぶ力」を育むために、どのように導けば良いのでしょうか。
「間違えたら友達に笑われるかも?」
新しいことに挑戦したり、人前で発表したりする場面で、そんな不安を感じる子どもは少なくありません。しかし、親や教師から「間違ってもいいよ」といわれることで安心したり、失敗を気にせずのびのびと振るまえるようになったりすることもあります。「間違えてもいい」「失敗も大切」と親や周囲が認識することの重要性、そして、子どもの「失敗から学ぶ力」を育むために、どのように導けば良いのでしょうか。
監修:正木大貴[博士(医学)]
1子どもはなぜ失敗を恐れる?
小学生の子どもが失敗を恐れる理由はさまざまです。ここではその主な理由を挙げていきます。

周囲からの評価が気になる
「失敗したら、お父さんやお母さん、先生に怒られるかも……」「友達に失敗を笑われたら恥ずかしい」、そんな風に考えて、挑戦するのをためらってしまう子どもがいるかもしれません。
失敗した場合、自分の能力や価値が否定されるのではないかと不安を感じ、周囲から受け入れられなくなるのではないかと恐れるからです。特に、過去に失敗したことでつらい思いや恥ずかしい思いをした経験がある子どもはなおさらでしょう。
また、最近はSNSやテレビなどで、失敗した人が強く批判されることが珍しくありません。その様子を目の当たりにした子どもが、「失敗すると、自分も責められるのでは」と怖くなり、リスクを取らない行動を選ぶことがあります。
失敗した場合、自分の能力や価値が否定されるのではないかと不安を感じ、周囲から受け入れられなくなるのではないかと恐れるからです。特に、過去に失敗したことでつらい思いや恥ずかしい思いをした経験がある子どもはなおさらでしょう。
また、最近はSNSやテレビなどで、失敗した人が強く批判されることが珍しくありません。その様子を目の当たりにした子どもが、「失敗すると、自分も責められるのでは」と怖くなり、リスクを取らない行動を選ぶことがあります。
完璧にやり遂げたいというこだわり
子どもが物事を完璧にやり切りたいと考えるタイプの場合、「失敗は許されないこと」と捉えがちです。常に完璧に、物事をやり遂げなければならないというプレッシャーが自らを追いつめ、失敗に対する過度の恐怖を引き起こしてしまいます。
親や先生をがっかりさせたくない
親や先生からの期待が高すぎると、子どもはその期待に応えられないことを恐れます。
例えばテストで90点をとったのに、「君の能力なら100点を取れるはずなのに」など、より上を目指すことを期待されると、失敗した時の周囲の失望感や叱責を恐れ、挑戦を避けるようになります。
例えばテストで90点をとったのに、「君の能力なら100点を取れるはずなのに」など、より上を目指すことを期待されると、失敗した時の周囲の失望感や叱責を恐れ、挑戦を避けるようになります。
予測がつかないことが怖い
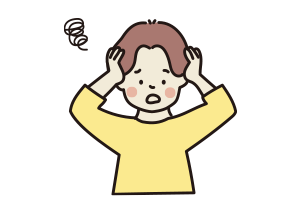
初めてやることや難しそうなことに対して強い不安を感じ、消極的になってしまう子どもは少なくありません。
また、失敗した時の周囲の反応が予測できず、やってみることをためらう子どももいます。
また、失敗した時の周囲の反応が予測できず、やってみることをためらう子どももいます。
成功体験が少なく、「どうせ失敗するから」と思い込んでしまう
過去に成功体験が少ない子どもは、「どうせ、自分は頑張っても失敗するんだ」と思い込みがちで、失敗への耐性が低く挑戦すること自体を避ける傾向があります。
失敗が許されない環境に置かれている
子どもの失敗を叱責する家庭や、失敗に対して厳しい評価がなされる学校など、失敗が許されない雰囲気が強い環境に置かれると、子どもが失敗を避けようとする傾向が強くなります。
恥をかきたくない、いつも完璧でいたい、親や先生の期待を裏切りたくない……。
失敗を恐れる理由を理解したうえで、「失敗は怖いものではなく、学びと成長の機会」と思える環境を整えることが、子どもが失敗を恐れず挑戦できるようになるためのカギとなります。
失敗を恐れる理由を理解したうえで、「失敗は怖いものではなく、学びと成長の機会」と思える環境を整えることが、子どもが失敗を恐れず挑戦できるようになるためのカギとなります。
2失敗体験は子どもが成長するチャンス
子どもはさまざまな理由で失敗を怖がりますが、失敗することで得られる力もあります。失敗を通して身につく力について説明します。
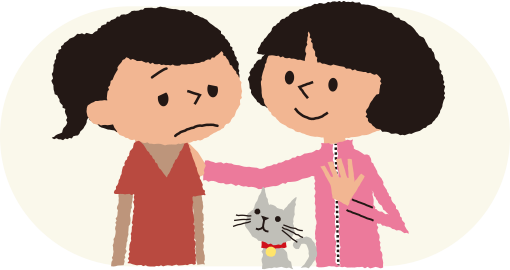
レジリエンス(回復力)が向上する
レジリエンスとは、つらいことや失敗があってもへこたれず、そこから学びを得て立ち直ろうとする力のことです。
レジリエンスが向上すれば、失敗して一時的に落ち込んだとしても、「悲しい」「恥ずかしい」「悔しい」という気持ちを切り替えることができたり、新しい挑戦をする際に不安に打ち勝つことができたりします。
失敗から学ぶ経験を通して、たくましく、そしてどんなことにも立ち向かえる力強い心が育まれていくはずです。
レジリエンスが向上すれば、失敗して一時的に落ち込んだとしても、「悲しい」「恥ずかしい」「悔しい」という気持ちを切り替えることができたり、新しい挑戦をする際に不安に打ち勝つことができたりします。
失敗から学ぶ経験を通して、たくましく、そしてどんなことにも立ち向かえる力強い心が育まれていくはずです。
問題解決力を伸ばすきっかけになる
「失敗は成功のもと」と言われるように、失敗は物事を成し遂げるまでの過程と捉えることができます。
失敗したという結果だけを見るのではなく、「どうすればうまくいくんだろう?」と、次の挑戦に活かすことを考えられるようになると、子どもの問題解決力の向上につながります。
失敗したという結果だけを見るのではなく、「どうすればうまくいくんだろう?」と、次の挑戦に活かすことを考えられるようになると、子どもの問題解決力の向上につながります。
他者への共感力が育つ
自分が失敗を経験することで、子どもは失敗がどのようなものか、失敗した時にどんな気持ちになるのかを理解します。この体験が、失敗した友達やきょうだいの気持ちを推し量る力につながります。
失敗を乗り越えた経験があれば、「失敗しても大丈夫。また挑戦すればいいんだよ」と、失敗した人を励ますこともできます。
失敗を乗り越えた経験があれば、「失敗しても大丈夫。また挑戦すればいいんだよ」と、失敗した人を励ますこともできます。
レジリエンスや問題解決力、共感力など失敗したからこそ身につき、子どもの成長を後押しする力も多くあります。
だからこそ、むやみに失敗を恐れる子どもになってほしくないものです。
3失敗を成長の糧に!親ができるサポート術
子どもが失敗から学び成長するために、親はどんなサポートをしてあげたらよいのでしょうか。ここでは、親にすすめたいサポート方法を紹介します。

日常生活で、様々なことに挑戦させてみる
様々なことに挑戦させて、成功したら褒めてあげ、失敗したら「失敗しても大丈夫だよ。やり直すうちに上手になっていくんだよ」と、繰り返し言葉で伝えることが大切です。また、結果に関係なく、新しいことに挑戦する勇気を持てたことをしっかり褒めてあげましょう。
さらに、言葉だけでなく行動で「失敗は怖くない」と理解させるために、子どもと一緒に料理やスポーツ、ゲーム、キャンプ、釣りなどのアクティビティをしたり、地域のイベントに参加したりすることもおすすめです。
料理なら「卵焼きがうまく折りたためない」「味が薄すぎた」などの失敗をしても、「スクランブルエッグにしちゃおう」「マヨネーズをかけたら美味しくなった!」など、やり方を変えたり、工夫をしたりすることで何とかなる体験をさせます。 習い事やなどは、よいきっかけになるはずです。
チャレンジを勧める時は、「~しなさい」と強制する言い方ではなく、「やってみる?」「お父さん(お母さん)と一緒にやってみない?」など、子どもが選べるような声かけをすると、子どもの自主性を尊重できます。
親や大人の目があるとプレッシャーを感じる子どもの場合は親が遠くで見守り、子どもたちだけで、あるいは一人だけで取り組ませてみましょう。誰の評価も気にする必要がない状況なら、大胆に挑戦できるはずです。
料理なら「卵焼きがうまく折りたためない」「味が薄すぎた」などの失敗をしても、「スクランブルエッグにしちゃおう」「マヨネーズをかけたら美味しくなった!」など、やり方を変えたり、工夫をしたりすることで何とかなる体験をさせます。 習い事やなどは、よいきっかけになるはずです。
チャレンジを勧める時は、「~しなさい」と強制する言い方ではなく、「やってみる?」「お父さん(お母さん)と一緒にやってみない?」など、子どもが選べるような声かけをすると、子どもの自主性を尊重できます。
親や大人の目があるとプレッシャーを感じる子どもの場合は親が遠くで見守り、子どもたちだけで、あるいは一人だけで取り組ませてみましょう。誰の評価も気にする必要がない状況なら、大胆に挑戦できるはずです。
親の失敗体験と、そこからの学びを共有する
「お父さんやお母さんも、子どもの頃は失敗ばかりだったんだよ」と、ちょっと笑える失敗談を話して聞かせてあげましょう。「失敗って恥ずかしいことじゃないんだ」と伝われば、子どもも気持ちが楽になるはずです。
また「お母さんはこんな失敗をしたけれど、いい勉強になった」と、失敗から何を学んだか、その学びがどんな役に立ったかを伝えれば、子どもを「失敗って、次に活かすことができるんだ」と気づくように導くことができます。
また「お母さんはこんな失敗をしたけれど、いい勉強になった」と、失敗から何を学んだか、その学びがどんな役に立ったかを伝えれば、子どもを「失敗って、次に活かすことができるんだ」と気づくように導くことができます。
頑張ってきたプロセスを認める

成功したという結果だけを褒めると、子どもは「失敗=駄目なこと」と捉えがちです。
失敗した時も、「残念だったけれど、ここまで頑張ってきた努力は絶対に無駄にならない。次に活かせるはずだよ」と、努力の過程を認める言葉をかけます。
そうすれば、子どもは失敗を恐れずにチャレンジする勇気を持ち、失敗から学ぶ力を身につけることができます。また、努力することの大切さや、諦めない心の強さを育むことにつながります。
失敗した時も、「残念だったけれど、ここまで頑張ってきた努力は絶対に無駄にならない。次に活かせるはずだよ」と、努力の過程を認める言葉をかけます。
そうすれば、子どもは失敗を恐れずにチャレンジする勇気を持ち、失敗から学ぶ力を身につけることができます。また、努力することの大切さや、諦めない心の強さを育むことにつながります。
子どもの失敗を責めたり、否定的な態度を取ったりしない
子どもの失敗に対し、「どうしてできないの?」「あーあ」など言葉で責めたり、ため息をついたり、不機嫌になったりするネガティブな反応をすると、子どもは「やってはいけないことをしてしまった」と考えるようになりがちです。
次第に臆病になり、「失敗して怒られるくらいなら」と、チャレンジすることをやめてしまいます。失敗して誰よりも落ち込んでいるのは子ども自身です。うまくいかなかった事実は受け止めつつ、親は次に活かすための方法を子どもと一緒に考えましょう。
次第に臆病になり、「失敗して怒られるくらいなら」と、チャレンジすることをやめてしまいます。失敗して誰よりも落ち込んでいるのは子ども自身です。うまくいかなかった事実は受け止めつつ、親は次に活かすための方法を子どもと一緒に考えましょう。
親が全て解決してしまわない
子どもに失敗させまいとして、親が先回りして指示したり、助言したりし過ぎないようにしましょう。子どもが失敗を通して解決策を考えたり、学んだりする機会を奪ってしまうことになります。
子ども自身に考える機会を与えなければ、失敗は失敗のままで終わってしまい、成功へのステップになりません。
また、「失敗しても親が何とかしてくれる」と他人任せな思考になってしまう恐れもあります。失敗をリカバリーする助言やサポートは行っても、親が後始末を肩代わりするのは避けましょう。
子ども自身に考える機会を与えなければ、失敗は失敗のままで終わってしまい、成功へのステップになりません。
また、「失敗しても親が何とかしてくれる」と他人任せな思考になってしまう恐れもあります。失敗をリカバリーする助言やサポートは行っても、親が後始末を肩代わりするのは避けましょう。
著名人の言葉や格言を知ることで、失敗に対するイメージを変える
大リーグ・ドジャース所属の大谷翔平は、失敗に対して「周りからは失敗に見えることでも、僕からしたら前へ進むための段階という場合があります。決して、後ろに下がっているわけではない」と発言しました。
また、南アフリカ共和国元大統領で、ノーベル平和賞受賞者のネルソン・マンデラは、「成功で私を判断しないでほしい。失敗から何度はい上がったかで判断してほしい」という言葉を残しています。
スポーツで前人未到の結果を残した選手や、世界に多大な影響を与えた人物でさえ失敗の経験をしているという事実は、子どもに勇気を与えるはずです。
また、南アフリカ共和国元大統領で、ノーベル平和賞受賞者のネルソン・マンデラは、「成功で私を判断しないでほしい。失敗から何度はい上がったかで判断してほしい」という言葉を残しています。
スポーツで前人未到の結果を残した選手や、世界に多大な影響を与えた人物でさえ失敗の経験をしているという事実は、子どもに勇気を与えるはずです。
親も新しいことにチャレンジする
子どもは親の行動をよく見ています。親が何かに挑戦し、結果に関わらずその挑戦を楽しむ姿を見せることは、子どもが「挑戦するって楽しいのかも」と感じることにつながります。
4親が「失敗してもいい」と思えることが大切

親が、子どもや自分たちの失敗に対して「当たり前のことで、失敗しても構わない」と受け入れることは、子どもの健全な成長において極めて重要です。なぜなら、親が失敗を受け入れる姿勢を持つことで、子どもが安心して新しいことに挑戦できる環境が整うからです。
親が必要以上に心配したりダメ出しばかりしたりすると、子どもにもその不安が伝わってしまい、挑戦する気持ちをなくしてしまうかもしれません。その結果、子どもは失敗を避けるために安全な選択を選びがちになり、成長の機会を逃してしまいかねません。
親が「失敗は成長のチャンス」と捉え、温かく見守ってあげることができれば、子どもは失敗から多くのことを学び、問題を解決する力や、逆境に負けない強い心を育んでいけるでしょう。
また、失敗は人生の自然な一部であり、それを乗り越えることで成長できるという健全な価値観を身につけることができます。
さらに、親が子どもの失敗に対して寛容である姿勢は、親子間の信頼関係を強くします。子どもは「失敗しても、親は自分を見放さない」という安心感を持つことで、困ったときに素直に相談できるようになり、より細やかなコミュニケーションが可能となるのです。
また、失敗は人生の自然な一部であり、それを乗り越えることで成長できるという健全な価値観を身につけることができます。
さらに、親が子どもの失敗に対して寛容である姿勢は、親子間の信頼関係を強くします。子どもは「失敗しても、親は自分を見放さない」という安心感を持つことで、困ったときに素直に相談できるようになり、より細やかなコミュニケーションが可能となるのです。
