column ココロの特集
子どもが小学校の先生と合わない!親はどうすればいい?

小学生は、学校での時間の大部分を先生とともに過ごします。そのため、先生との相性は子どもの学校生活に大きな影響を与えるといえます。しかし、もし子どもと先生との関係がスムーズでないとしたら、どうしたらよいでしょうか。
この記事では、子どもが先生と合わない際に見られうるサインやその原因、親が子どもをサポートする方法、「モンスターペアレンツ」と思われずに先生との良好な関係を維持するためのポイントなどについて、詳しく解説します。先生との関係を改善し、子どもの学校生活をより充実したものにするヒントが得られるはずです。
この記事では、子どもが先生と合わない際に見られうるサインやその原因、親が子どもをサポートする方法、「モンスターペアレンツ」と思われずに先生との良好な関係を維持するためのポイントなどについて、詳しく解説します。先生との関係を改善し、子どもの学校生活をより充実したものにするヒントが得られるはずです。
監修:正木大貴[博士(医学)]
もくじ
1子どもと先生との関係がうまくいかない原因は?
公益社団法人「子どもの発達科学研究所」と浜松医科大学「子どものこころの発達研究センター」の調査(2024年3月)で、不登校の原因として「先生と合わなかった」を挙げた児童が35.9%と報告されました。
担任をはじめとする先生との関係が、小学生の学校生活に大きな影響を与えていることがよくわかります。
子どもと先生がうまくいかない原因は、どこにあるのでしょうか。
担任をはじめとする先生との関係が、小学生の学校生活に大きな影響を与えていることがよくわかります。
子どもと先生がうまくいかない原因は、どこにあるのでしょうか。
コミュニケーションがうまくとれていない
先生との関係が上手くいかない原因の1つに、コミュニケーションの問題があります。
特に小学校低学年では、先生に対する緊張や不安、そして親や親類以外の大人に慣れていないなどの理由から、十分なコミュニケーションが取れないことが珍しくありません。
特に小学校低学年では、先生に対する緊張や不安、そして親や親類以外の大人に慣れていないなどの理由から、十分なコミュニケーションが取れないことが珍しくありません。
- 困ったことがあっても、気おくれして先生に相談できない
- 先生の指示が理解できないが、そのことを伝えられない
- 「こんなことを言ったら叱られるのでは」と不安で、思ったことを素直に言えない
などのケースが考えられます。
相性が合わない
子どもと先生の相性が合わない場合は、良い関係が築きにくい傾向があります。例えば、以下のようなケースが考えられます。
- おとなしい子どもと、「もっと元気に!」と激励する熱血型の先生
- 自分なりのこだわりや意見がある子どもと、一方的な指示をする先生
先生と生徒とはいえ、性格や態度の好き嫌いなど、人として相性が良くないこともありえます。そのような場合、子どもは先生に対して抵抗感を持ってしまうかもしれません。
先生への指導方針に不満がある
子どもが先生の指導方針に不満を持つことで、先生との関係がうまくいかなくなることもあります。例えば、以下のようなケースが考えられます。
- 先生が特定の生徒をえこひいきする
- 先生の指導が厳しすぎる
- 授業以外はあまり構ってくれない
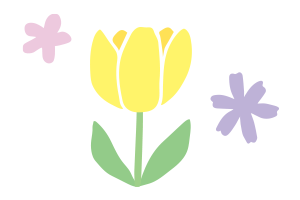
小学生(6歳~12歳)は、社会性が発達する重要な時期であり、先生の言動が行動規範に大きく影響すると考えられます。そのため先生の指導方針に敏感で、不公平な扱いを受けていると感じたり、厳しすぎる指導や構ってくれないことに不満を持ったりすることがあります。
これらの問題に早期に対応するためには、子どもと先生の関係に何らかの支障が生じているかもしれないサインに気をつけてみましょう。
では、具体的にどのようなサインに注意を払えばよいのでしょうか。
では、具体的にどのようなサインに注意を払えばよいのでしょうか。
2子どもと先生がうまくいっていないかも?
注意したいサインとは
小学生の子どもにとって、先生との関係は非常に重要です。子どもが学校で先生と過ごす時間が長いため、先生との相性は学習意欲や心の安定に大きく影響するからです。
先生との良好な関係は、子どもの学習意欲を高め、健全な学校生活を送るための基盤となります。一方で、先生との関係が悪化すると、学習面でのつまずきだけでなく、心身の不調にもつながる可能性があります。そのため、子どもと先生の関係に違和感を覚えたら、早めに気づき対処することが重要です。
先生との良好な関係は、子どもの学習意欲を高め、健全な学校生活を送るための基盤となります。一方で、先生との関係が悪化すると、学習面でのつまずきだけでなく、心身の不調にもつながる可能性があります。そのため、子どもと先生の関係に違和感を覚えたら、早めに気づき対処することが重要です。

子どもからのこんなサインに注意
子どもが何らかのストレスを抱えている場合、以下のようなサインが現れることがあります。
【生活面】
- 朝、布団から出たがらない
- 夜ふかしや寝坊など、生活リズムが乱れている
これらは、学校に行くことへの不安や抵抗感の表れかもしれません。
【身体面】
- 朝になると腹痛や頭痛を訴える
- 以前より元気がない
- 食欲が落ちている
ストレスによる心身の不調が、このような形で現れることがあります。
【精神面】
- 怒りっぽくなる、よく泣くなど、感情の起伏が激しくなる
- 目に見えて口数が少なくなる
ストレスにより、精神的に不安定な様子が見られることがあります。
【学習面】
- それまで好きだった教科の成績が急に下がる
- 宿題をやりたがらない
- 勉強に対する意欲が大きく低下する
先生との関係悪化は、学習意欲の低下につながりやすいと考えられます。
サインの見分け方と対処法

上記のサインは、友達関係の悩みや授業についていけないなど、他の原因でも起こり得ます。そのため、単にサインを見るだけでは、先生との関係に問題があるかどうかの判断は難しいでしょう。
サインの原因を見分けるためには、普段から子どもの様子をよく見ることが大切です。例えば、先生に対する否定的な発言が増える、先生のことを話したがらない、先生の反応を気にする様子が見られるなどの変化があれば、先生との関係に何か問題があるようだと気づくことができます。
そういった変化があれば、まず子どもとの対話を心がけてください。対話のきっかけを作るには、「学校で何か困ることはない?」「先生のことで、気になることはある?」などの言葉がけをするとよいでしょう。
子どもの話を聞く時は、問い詰めるような聞き方は避け、子どもの話にじっくりと耳を傾けることが大切です。
サインの原因を見分けるためには、普段から子どもの様子をよく見ることが大切です。例えば、先生に対する否定的な発言が増える、先生のことを話したがらない、先生の反応を気にする様子が見られるなどの変化があれば、先生との関係に何か問題があるようだと気づくことができます。
そういった変化があれば、まず子どもとの対話を心がけてください。対話のきっかけを作るには、「学校で何か困ることはない?」「先生のことで、気になることはある?」などの言葉がけをするとよいでしょう。
子どもの話を聞く時は、問い詰めるような聞き方は避け、子どもの話にじっくりと耳を傾けることが大切です。
3子どもと先生の関係改善のため、親ができるサポート
子どもの話を聞いて、実際に先生との関係がスムーズにいっていない場合、親は関係改善のために何をすべきでしょうか。
ここでは、親ができる具体的なサポートについて考えます。
ここでは、親ができる具体的なサポートについて考えます。

子どもの話を聞く
子どもが先生と合わないと感じている場合、まずは子どもの話を聞くことが大切です。
【具体的な聞き方のポイント】
- 「『この先生とは合わないな』と思ったのはなぜ?どんなことがあったの?」と事実を確認する
- 事実を確認した後、「そんなことがあったんだね。その時、どんな気持ちだった?」と、子どもの気持ちを聞き、「それは悲しかったね、いやだったね」と感情を受け止める
- 「先生は、なぜそうしたと思う?」と、先生の視点に立って考えさせる
【注意!避けたい対応】
- 子どもの話をすべて鵜呑みにして判断する
- 「先生が悪い」と決めつけ、批判する
- 「先生も大変なんだから、我慢しなさい」と一方的に諭す
子どもの話を聞く際は、子どもを応援する姿勢を示しながらも、客観的な立場を保つことが重要です。子どもの話を鵜呑みにせず、先生の立場にも立って考えてみましょう。
また、子どもと一緒になって先生の悪口を言うのは避けてください。親の態度を見て、子どもが「人のことを、こんな風に悪く言ってもいいんだ」と学習してしまうのを避けるためです。
また、子どもと一緒になって先生の悪口を言うのは避けてください。親の態度を見て、子どもが「人のことを、こんな風に悪く言ってもいいんだ」と学習してしまうのを避けるためです。
先生と建設的な対話の機会をもつ
子どもの話を聞いた上で、先生にも問題があると感じた場合や、改めてもらいたい点がある場合などは、先生に面談を申し入れるとよいでしょう。
面談の際は、以下のようなポイントを押さえておきましょう。
面談の際は、以下のようなポイントを押さえておきましょう。
【面談前の準備】
- 具体的な出来事や状況についてメモしておく
- 子どもが困っている点を整理する
- 「こうしてほしい」という要望をはっきりさせる
- 自分なりの改善案を考えておく
【面談時に意識すること】
- 「お互いによい関係を築くことが目的」という、前向きな姿勢で臨む
- 客観的な事実を基に、感情的にならず冷静に話し合う
- 強い言葉を使うのを避け、謙虚さをもって話す
- 先生の指導方針や意見もしっかり確認する
話し方で意識したいのは、感情的にならず、冷静に要望を伝えることです。また、謙虚な姿勢で臨むことも忘れずに。
なお、当人と話して改善が見込めなさそうな場合は、学年主任の先生や校長先生などに相談し、「●●先生とうちの子どもがどうしても合わないようなので、解決策を検討していただけませんか」とお願いする方法もあります。
なお、当人と話して改善が見込めなさそうな場合は、学年主任の先生や校長先生などに相談し、「●●先生とうちの子どもがどうしても合わないようなので、解決策を検討していただけませんか」とお願いする方法もあります。
ママ友に聞いてみる
同じクラスのママ友に、お子さんと先生との関係について聞いてみるのもよいでしょう。他の子どもたちはどのように先生と接しているのか、先生の指導方針についてどう感じているのかなど、参考になる情報が得られるかもしれません。
継続的なサポート体制を作る
- 連絡帳やアプリなどを活用した情報共有(月に1、2回程度)
- 年2回程度の個人面談以外に、必要に応じて面談をお願いする
- 授業参観や保護者会など、学校行事への積極的な参加
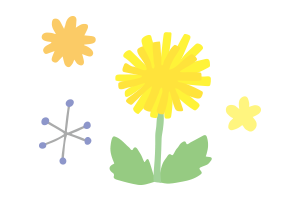
継続的なサポートを行うために、学校との連携を密にすることも効果的です。連絡帳や電話、また学校と親の連絡手段としてアプリなどを活用している場合はそういった方法も利用して、こまめに連絡を取り合いましょう。
ただし、度を越えた頻度で連絡すると先生に敬遠されたり、「モンスターペアレンツ」扱いされることがあったりするかもしれませんから、節度を守りましょう。
ただし、度を越えた頻度で連絡すると先生に敬遠されたり、「モンスターペアレンツ」扱いされることがあったりするかもしれませんから、節度を守りましょう。
これらの具体的な対応は、子どもと先生の関係改善をサポートすることにつながります。
4親が先生との良好な関係を維持するためのポイント
子どもと先生の良好な関係を維持するには、親も先生と良い関係を保つことが必要です。では、親はどのような対応を心がけるべきでしょうか。

先生に対し礼儀正しい態度をとる
先生との良好な関係を維持するためには、親自身が礼儀正しい態度を取ることが大切です。
例えば、先生に連絡する際には丁寧な言葉遣いを心がける、面談時には時間を厳守する、行事や保護者会などにはできるだけ協力するなどです。
また、子どもの良い変化や成長について、指導に対する感謝の気持ちを伝えることも、良い関係づくりのために効果的です。
例えば、先生に連絡する際には丁寧な言葉遣いを心がける、面談時には時間を厳守する、行事や保護者会などにはできるだけ協力するなどです。
また、子どもの良い変化や成長について、指導に対する感謝の気持ちを伝えることも、良い関係づくりのために効果的です。
先生と適度な距離感を保つ
先生とは適度な距離感を保つことが重要です。親しすぎず、かといって疎遠すぎてもいけません。
子どもについて必要な情報は共有することが望ましいですが、過度な連絡や親密すぎる態度、個人的な贈り物などは避けるべきです。
子どもについて必要な情報は共有することが望ましいですが、過度な連絡や親密すぎる態度、個人的な贈り物などは避けるべきです。
先生のアドバイスを尊重する
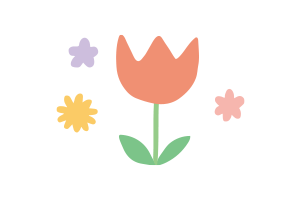
先生から子どもへのアドバイスがあった場合は、先生の意図を理解し、必要であると思えたら段階的に取り入れることを検討してください。
疑問点がある場合は、クレームととられないよう、建設的な対話を意識することが重要です。
例えば、「先生のご意見に対し、子どもは実行することが難しいと感じているようです。ご意見とは少し異なりますが、●●のような対応は可能でしょうか?」のように、問題点を挙げた上で、別案を提示するなど、協力的な態度が望ましいです。
先生は子どもの成長を願って助言してくれているはずですから、一方的な要求や批判は避け、「子どもの成長のために、一緒に考えたい」という姿勢を示しましょう。
疑問点がある場合は、クレームととられないよう、建設的な対話を意識することが重要です。
例えば、「先生のご意見に対し、子どもは実行することが難しいと感じているようです。ご意見とは少し異なりますが、●●のような対応は可能でしょうか?」のように、問題点を挙げた上で、別案を提示するなど、協力的な態度が望ましいです。
先生は子どもの成長を願って助言してくれているはずですから、一方的な要求や批判は避け、「子どもの成長のために、一緒に考えたい」という姿勢を示しましょう。
先生の言動について、子どもが理解できるようフォローする
先生の言動を子どもが理解できない時は、親が先生との橋渡し役として、子どもの理解を手助けするのも、子どもと先生の関係を改善する1つの方法です。
例えば、「お母さん(お父さん)は、同じ大人としてわかるんだけれど、きっと先生はこう言いたかったんじゃないかな」と説明し、子どもの理解を促します。
例えば、子どもが「本読みを当てられたんだけど、先生に『もっと元気に読めるように、頑張ろう!』っていわれたの。ちゃんと読んでいたのに」と納得がいかない様子をしていたら、「もしかしたら、先生には聞こえにくかったのかもしれないね。それとも、●●ちゃんの元気な声を聞きたかったのかもね」と伝えてみると良いかもしれません。
例えば、「お母さん(お父さん)は、同じ大人としてわかるんだけれど、きっと先生はこう言いたかったんじゃないかな」と説明し、子どもの理解を促します。
例えば、子どもが「本読みを当てられたんだけど、先生に『もっと元気に読めるように、頑張ろう!』っていわれたの。ちゃんと読んでいたのに」と納得がいかない様子をしていたら、「もしかしたら、先生には聞こえにくかったのかもしれないね。それとも、●●ちゃんの元気な声を聞きたかったのかもね」と伝えてみると良いかもしれません。
5子どもと先生の関係改善に、親ができることはたくさんある!
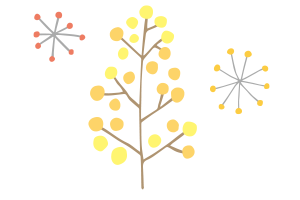
子どもが先生と合わないと感じる場面は、実は、小学校の生活の中でよくあることといえます。しかし、そのような状況は、親が適切に対応することで改善できる可能性が十分にあります。
重要なのは、「子どもの様子の変化に早めに気付き、丁寧に話を聞く」「先生と建設的な対話を心がけ、協力的な態度で接する」「感情的にならず、冷静に状況を判断する」という3点です。
親は、適切なサポートを通して、子どもと先生の架け橋となることができます。一方的な批判や要求は避け、「子どもの成長のために一緒に考えていく」という姿勢で臨むことを忘れないでください。
すぐに劇的な改善は望めないかもしれませんが、焦らず、粘り強く取り組むことで、必ず道は開けるはずです。子どもが充実した学校生活を送れるよう、親としてできることから始めていきましょう。
重要なのは、「子どもの様子の変化に早めに気付き、丁寧に話を聞く」「先生と建設的な対話を心がけ、協力的な態度で接する」「感情的にならず、冷静に状況を判断する」という3点です。
親は、適切なサポートを通して、子どもと先生の架け橋となることができます。一方的な批判や要求は避け、「子どもの成長のために一緒に考えていく」という姿勢で臨むことを忘れないでください。
すぐに劇的な改善は望めないかもしれませんが、焦らず、粘り強く取り組むことで、必ず道は開けるはずです。子どもが充実した学校生活を送れるよう、親としてできることから始めていきましょう。
