column ココロの特集
子どもの「好き」を未来へつなぐ! 小学生から始めるわくわくキャリア教育

テクノロジーの進化やグローバル化など、さまざまな要因により職業環境が急速に変化した現在。子どもたちが大人になる頃には、この変化はさらに加速しているでしょう。
そんな時代を生きるには、定型的なキャリアパスにとらわれず、柔軟に自分の道を切り拓く力が求められます。その力の源は「好き!」との出会い。熱中する体験を通じて、子どもは「強み」や「自分らしさ」を発見し、可能性を広げていきます。
この記事では、子どもの「好き」を将来につなげる親子の関わり方をご紹介します。「好き」を通し、子どものキャリアを親子で考える一歩にしてください。
そんな時代を生きるには、定型的なキャリアパスにとらわれず、柔軟に自分の道を切り拓く力が求められます。その力の源は「好き!」との出会い。熱中する体験を通じて、子どもは「強み」や「自分らしさ」を発見し、可能性を広げていきます。
この記事では、子どもの「好き」を将来につなげる親子の関わり方をご紹介します。「好き」を通し、子どものキャリアを親子で考える一歩にしてください。
監修:正木大貴[博士(医学)]
もくじ
1小学生のキャリア教育が注目されるのはなぜ?
「キャリア教育」と聞くと、高校生や大学生を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし昨今、文部科学省は小学生からのキャリア教育を重視し、力を入れています。
2022年3月に公表された「小学校キャリア教育の手引き」では、人生100年時代の到来を見据え、小学校からのキャリア形成の重要性が強調されています。
なぜ近年、小学生でのキャリア教育が注目されているのか、その理由を紹介します。
2022年3月に公表された「小学校キャリア教育の手引き」では、人生100年時代の到来を見据え、小学校からのキャリア形成の重要性が強調されています。
なぜ近年、小学生でのキャリア教育が注目されているのか、その理由を紹介します。
小学生のキャリア教育が注目される理由
① 安定志向の限界

親世代が学生だった頃、理想的なキャリアモデルとされていたのは「安定した会社に就職すること」ではないでしょうか。
かつては「大企業に入れば定年退職まで安泰」と考えられ、多くの人がその道を目指しました。しかし2000年以降、デジタル技術の急速な発展、環境問題や国際情勢の変化などにより、社会構造は大きく変化しています。
さらに2008年のリーマンショック、2020年の新型コロナウイルス感染拡大など、予期せぬ出来事で経済環境が一変することも経験してきました。終身雇用制度は崩れ、企業の寿命も短くなっています。
子どもたちが大人になる頃には、社会はさらに大きく変化しているでしょう。そのような時代に「これが絶対に安心・安全」という王道的なキャリアモデルはもはや存在せず、むしろ変化に柔軟に対応し、自ら新しい価値を生み出す力が求められるようになっています。
かつては「大企業に入れば定年退職まで安泰」と考えられ、多くの人がその道を目指しました。しかし2000年以降、デジタル技術の急速な発展、環境問題や国際情勢の変化などにより、社会構造は大きく変化しています。
さらに2008年のリーマンショック、2020年の新型コロナウイルス感染拡大など、予期せぬ出来事で経済環境が一変することも経験してきました。終身雇用制度は崩れ、企業の寿命も短くなっています。
子どもたちが大人になる頃には、社会はさらに大きく変化しているでしょう。そのような時代に「これが絶対に安心・安全」という王道的なキャリアモデルはもはや存在せず、むしろ変化に柔軟に対応し、自ら新しい価値を生み出す力が求められるようになっています。
② DX(デジタルトランスフォーメーション)による仕事の変化
DXは多くの産業に影響を与えています。例えばAIやロボティクス(ロボット工学)の発展により、コールセンターやスーパー・コンビニのレジなど、定型的な業務は徐々に自動化されつつあります。
その一方で、新たな職種も次々と生まれています。10年前には、現在の「YouTuber」や「AIエンジニア」などの職業は今ほど身近ではありませんでした。子どもたちは、親世代が想像もしていなかった職業に就く可能性があるのです。
このような時代には、デジタルリテラシー(ITツールを活用する能力)とアナログスキル(人間にしかできない創造性や共感力)の両方が求められます。
例えば、情報があふれる現代社会では、膨大な情報の中から必要なものを選び出し、適切に活用する力が不可欠です。また新型コロナウイルス感染拡大を経て、リモートワークやオンライン会議など、ネット上でのコミュニケーション能力も、今や基本的なスキルといえます。
テクノロジーを使いこなす力と、人間ならではの感性や思考力を併せ持つことが、これからの社会で活躍するためのカギとなるでしょう。
その一方で、新たな職種も次々と生まれています。10年前には、現在の「YouTuber」や「AIエンジニア」などの職業は今ほど身近ではありませんでした。子どもたちは、親世代が想像もしていなかった職業に就く可能性があるのです。
このような時代には、デジタルリテラシー(ITツールを活用する能力)とアナログスキル(人間にしかできない創造性や共感力)の両方が求められます。
例えば、情報があふれる現代社会では、膨大な情報の中から必要なものを選び出し、適切に活用する力が不可欠です。また新型コロナウイルス感染拡大を経て、リモートワークやオンライン会議など、ネット上でのコミュニケーション能力も、今や基本的なスキルといえます。
テクノロジーを使いこなす力と、人間ならではの感性や思考力を併せ持つことが、これからの社会で活躍するためのカギとなるでしょう。
文部科学省は「小学校キャリア教育の手引き」に先立ち、2020年3月の「新学習指導要領」で、これからの時代に必要な力として「生きる力」を掲げています。
これは変化する社会の中で、自分で課題を見つけ、自ら学び、考え、判断して行動し、よりよい社会や人生を切り拓いていく力を指しています。
現在は、単に「将来なりたい職業」を考えるだけでなく、子どもの頃から自分の興味・関心を広げ、様々な経験を通じて「やってみたい」「できるようになりたい」という意欲を育むことが重要な時代になっています。
小学生の段階からのキャリア教育は、職業選択のためだけではなく、子どもたちが自分の人生を自分らしく生きるための土台づくりと言えるでしょう。「好き」を大切にし、それを育む姿勢は、変化の激しい時代を生き抜くための重要な力となります。
続いて、子どもの「好き」の中に隠れている可能性について、具体的に紹介していきます。
これは変化する社会の中で、自分で課題を見つけ、自ら学び、考え、判断して行動し、よりよい社会や人生を切り拓いていく力を指しています。
現在は、単に「将来なりたい職業」を考えるだけでなく、子どもの頃から自分の興味・関心を広げ、様々な経験を通じて「やってみたい」「できるようになりたい」という意欲を育むことが重要な時代になっています。
小学生の段階からのキャリア教育は、職業選択のためだけではなく、子どもたちが自分の人生を自分らしく生きるための土台づくりと言えるでしょう。「好き」を大切にし、それを育む姿勢は、変化の激しい時代を生き抜くための重要な力となります。
続いて、子どもの「好き」の中に隠れている可能性について、具体的に紹介していきます。
2子どもの「好き」に、可能性は隠れている!
子どもたちが生き生きと輝く瞬間、それは多くの場合、「好き」なことに取り組んでいるときです。「好き」の中に、子どもの将来を豊かに彩る可能性の種が隠れています。
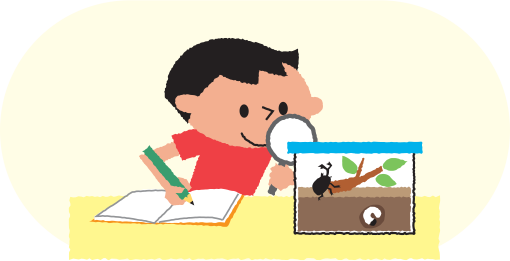
没頭する瞬間に見える、子どもの適性
子どもの本当の強みは、学校の成績だけでは見えてきません。日常生活の中で、子どもが心から没頭している瞬間こそ、その子の適性や才能が自然と表れています。
例えば、虫を観察する時間。普段はおしゃべりな子が、黙り込んで一心不乱に観察を始め、虫の動きや特徴を細部まで見逃さないその集中力は、生物学者のような観察眼と言えるかもしれません。
あるいは、ゲームアプリで遊ぶ時間。例えば、仮想空間の中で道具や建物を作る「マインクラフト」で、何時間でも集中して複雑な構造物を作り上げるときに、空間認識能力や論理的思考、そして創造性が発揮されています。
こうした日常の「好き」に表れる子どもの特性は、将来のキャリアにおける強みになる可能性を秘めています。集中力、観察力、創造性、論理的思考……これらはどんな仕事にも活かせる普遍的な力です。
例えば、虫を観察する時間。普段はおしゃべりな子が、黙り込んで一心不乱に観察を始め、虫の動きや特徴を細部まで見逃さないその集中力は、生物学者のような観察眼と言えるかもしれません。
あるいは、ゲームアプリで遊ぶ時間。例えば、仮想空間の中で道具や建物を作る「マインクラフト」で、何時間でも集中して複雑な構造物を作り上げるときに、空間認識能力や論理的思考、そして創造性が発揮されています。
こうした日常の「好き」に表れる子どもの特性は、将来のキャリアにおける強みになる可能性を秘めています。集中力、観察力、創造性、論理的思考……これらはどんな仕事にも活かせる普遍的な力です。
「好き」を大切にすべき理由
理由① 未来の社会では個性が価値を持つから
AIが発達する社会では、「定型的な作業はAIやロボットに任せ、人間は創造性や独自の視点を活かした仕事に集中しよう」という意識が高まります。そこで重要になるのが、その人ならではの個性や視点です。
「誰にでもできること」ではなく、「自分だからこそできること」が価値を持つ時代になりつつあります。子どもの個性を尊重し、その子らしい興味関心を大切にすることは、将来の可能性を広げる土台となるのです。
「誰にでもできること」ではなく、「自分だからこそできること」が価値を持つ時代になりつつあります。子どもの個性を尊重し、その子らしい興味関心を大切にすることは、将来の可能性を広げる土台となるのです。
理由② 自分から進んで続けられる原動力になるから
「好き」という感情は、何かを続ける上で非常に強い原動力になります。好きだからこそ困難があっても挑戦し続けられ、自ら学び、深めようとする姿勢が生まれるのです。
「これが好きで続けたいから、少々の苦労なら乗り越えよう」と思える対象に出会うことは、人生の幸福度にも大きく影響します。子どもの「好き」を尊重し応援することは、生涯学習の基盤となり、将来の人生満足度にもつながるといえるでしょう。
実際、職場での満足度調査では、給与や待遇だけでなく「仕事のやりがい」や「自己成長の機会」を重視する傾向が強まっています。
「これが好きで続けたいから、少々の苦労なら乗り越えよう」と思える対象に出会うことは、人生の幸福度にも大きく影響します。子どもの「好き」を尊重し応援することは、生涯学習の基盤となり、将来の人生満足度にもつながるといえるでしょう。
実際、職場での満足度調査では、給与や待遇だけでなく「仕事のやりがい」や「自己成長の機会」を重視する傾向が強まっています。
子どもの「好き」を、単なる一過性の興味や、大人になったら卒業すべき「子どもっぽいもの」と決めつけることはありません。将来花開く才能や、社会に貢献できる専門性の種が隠れていることも珍しくないのです。
子どもが心から楽しめる「好き」を大切に育てることが、予測困難な未来を生き抜く力につながるのではないでしょうか。
次に、そんな子どもの「好き」との出会いを促し、深めるにはどうしたらよいか考えてみましょう。
子どもが心から楽しめる「好き」を大切に育てることが、予測困難な未来を生き抜く力につながるのではないでしょうか。
次に、そんな子どもの「好き」との出会いを促し、深めるにはどうしたらよいか考えてみましょう。
3子どもの「好き」との出会いと向き合い方は?
子どもが「好き」に出会い、それが自然に発展していくプロセスを理解することは、適切なサポートの第一歩です。ここでは、子どもの「好き」との出会いのきっかけと、その内面的な発展プロセスについて考えていきましょう。

「好き」と出会うには、さまざまな体験をすること
子どもの「好き」は、多様な体験の中から生まれます。「やってみたら楽しかった」「これ、おもしろい!」という感動が、「好き」の種になるのです。
家庭でできる体験は、料理、園芸、工作、読書、スポーツ、音楽鑑賞などさまざま。休日には、美術館や博物館などに連れていくことも、「好き」を見つけるよい機会です。
また、地域のワークショップや体験教室も、新しい「好き」と出会うチャンスになります。
重要なのは、子どもの反応を見守ること。「これは楽しそう!」と目を輝かせる瞬間を見逃さないようにしましょう。そして、「やってみたい」という意欲が芽生えたら、それを応援してください。
家庭でできる体験は、料理、園芸、工作、読書、スポーツ、音楽鑑賞などさまざま。休日には、美術館や博物館などに連れていくことも、「好き」を見つけるよい機会です。
また、地域のワークショップや体験教室も、新しい「好き」と出会うチャンスになります。
重要なのは、子どもの反応を見守ること。「これは楽しそう!」と目を輝かせる瞬間を見逃さないようにしましょう。そして、「やってみたい」という意欲が芽生えたら、それを応援してください。
子どもの内面で起こる「好き」の深まり方を知る
子どもの「好き」は、自然な流れの中でさまざまな形で深まっていくことがあります。
このような変化の過程を観察することで、子どもの興味関心の発展に合わせた関わり方のヒントが得られるかもしれません。
このような変化の過程を観察することで、子どもの興味関心の発展に合わせた関わり方のヒントが得られるかもしれません。
「好き」が広がり、深まっていく様子

「好き」なことを続けていると、子どもの興味の広がり方や深まり方に、いくつかの特徴的なパターンが見られることがあります。以下はそうした変化の一例です。
①純粋な興味と模倣の時期
子どもが何かに夢中になる最初のきっかけは、単に「楽しい」「面白い」という感覚であることが多いようです。例えば、プログラミングに興味を持ち始めた子どもは、サンプルコードをそのまま試したり、基本的な命令を覚えたりすることを楽しむことがあります。②知識への好奇心が広がる時期
興味を持ち続けると、より専門的な知識への好奇心が芽生えることもあります。宇宙が好きな子どもの場合、単に惑星の名前を覚えるだけでなく、「なぜ土星には輪があるの?」「ブラックホールはどうやってできるの?」といった疑問を持つようになる姿が見られるかもしれません。③技術や創造性が深まる時期
さらに関心が続くと、技術的な向上や創造的な応用に関心が向くことがあります。たとえば、思いのままに絵を描いていた子どもが、「遠近法を使うとどう見えるか」「影の付け方でどう印象が変わるか」といった技術的な側面に興味を示すようになることもあります。④関連する分野へ興味が広がる時期
「好き」なことが、関連する様々な分野への興味につながることも少なくありません。例えば料理が好きな子どもが、化学(調理による物質の変化)や文化(世界各国の食文化)など、多方面に関心を広げていくこともあるでしょう。
これらの変化は、すべての子どもに当てはまるわけではありません。
また必ずしもこの順序で進むわけではなく、同時に複数の特徴が現れることもあれば、まったく異なる形で興味が発展することもあります。
大切なのは、子どもそれぞれの関心の変化を見守りながら、その時々の興味に合わせたサポートを考えることです。
これらは確立された発達理論ではなく、子どもたちの興味の広がり方について考える際の一つの視点として参考にしていただければと思います。
また必ずしもこの順序で進むわけではなく、同時に複数の特徴が現れることもあれば、まったく異なる形で興味が発展することもあります。
大切なのは、子どもそれぞれの関心の変化を見守りながら、その時々の興味に合わせたサポートを考えることです。
これらは確立された発達理論ではなく、子どもたちの興味の広がり方について考える際の一つの視点として参考にしていただければと思います。
子どもが何を「好き」なのか、解像度を上げてみる
「好き」と一言で言っても、その内容は多面的です。「電車が好き」「ゲームが好き」と表面的に捉えるのではなく、もう一歩踏み込んで、何がその子を惹きつけているのかを理解することで、将来のキャリアにつながる可能性が広がります。
「好き」の多面性を理解する

子どもの「好き」を理解するためには、一見、単純な興味の中に隠れている多様な側面を見つけることが大切です。同じ「好き」でも、子どもによって着目するポイントは異なります。例を挙げて説明します。
①「電車が好き」という場合
「電車が好き」という場合は、いくつかの側面があります。
- 観察・記録的な側面
- 駅に行って電車の種類や時刻を記録したり、写真を撮ったりする子どもは、データ収集や記録が好きなタイプです。この特性は、写真家やジャーナリスト、あるいはデータアナリストとしての才能につながるかもしれません。
- 技術的な側面
- 電車の構造や動く仕組みに興味を持ち、プラレールで複雑な線路を組み立てる子どもは、機械工学や設計に関心があるのかもしれません。将来、エンジニアや設計士としての道が開ける可能性があります。
- 社会的な側面
- 路線図を眺めて「なぜこの駅とこの駅が繋がっているんだろう?」と考えることが好きな子どもは、交通システムやまちづくりに興味があるのかもしれません。都市計画や交通政策、環境問題に取り組む仕事につながる可能性があります。
②「マインクラフトが好き」という場合
人気ゲーム「マインクラフト」に夢中になっている子どもも、さまざまな側面から見ることができます。
- 建築的な側面
- 美しい建物や街を作るのが好きな子どもは、空間デザインの才能があるかもしれません。この興味は、3D設計、建築、都市計画などの分野につながる可能性があります。
- プログラミング的な側面
- 「マインクラフト」の「レッドストーン回路」と呼ばれる仕組みを使って自動装置を作るのが好きな子どもは、論理的思考力とプログラミングの素質があるのかもしれません。コーディングやシステム設計の分野で才能を発揮する可能性があります。
- 社会的な側面
- オンラインで友達と協力して大きなプロジェクトを作る子どもは、コミュニケーション能力やリーダーシップを発揮しています。将来、コミュニティ運営やチームマネジメントの仕事で活躍できるかもしれません。
次へのステップ:「好き」を深めるサポート
子どもの「好き」の多面性を理解したら、次は適切なサポートが重要です。子どもの関心に合わせた本や動画の提案、関連するワークショップや体験活動の情報提供など、興味を深めるリソースを提供しましょう。子どもの「好き」が単なる趣味から、より専門的な興味へと発展する橋渡しとなります。
これらのサポートの具体的方法については、次の章で詳しく見ていきましょう。
これらのサポートの具体的方法については、次の章で詳しく見ていきましょう。
4子どもの「好き」を応援するために親ができること
子どもの「好き」は、将来の可能性を広げる貴重な種。その種が芽吹き、すくすくと育つためには、親のサポートが欠かせません。
しかし、親が熱心すぎるあまり子どもの主体性を奪ってしまったり、逆に親の関心が薄すぎて子どもの才能の芽を見逃してしまったりすることもありえます。
ここでは、子どもの「好き」を健全に応援するための、親の関わり方について考えます。
しかし、親が熱心すぎるあまり子どもの主体性を奪ってしまったり、逆に親の関心が薄すぎて子どもの才能の芽を見逃してしまったりすることもありえます。
ここでは、子どもの「好き」を健全に応援するための、親の関わり方について考えます。

基本的な関わり方
「好き」への共感と理解
子どもの「好き」に共感することは、親子のつながりを深める素晴らしい機会です。「どうしてそれが好きなの?」と尋ねて、子どもの話に耳を傾けてみましょう。
例えば、宇宙に興味がある子どもなら「月と火星、どっちに行ってみたい?」「宇宙飛行士になったら何をしてみたい?」と会話を広げてみる。
料理が好きな子どもなら「その料理を上手に作るコツは?」「次は何を作りたいの?」と興味を示すことで、子どもは自分の「好き」を認めてもらえたという安心感を得られます。
たとえ親自身が興味のない分野でも、子どもの目線に立って「なるほど、そういうところが面白いんだね」と理解しようとする姿勢が大切です。
例えば、宇宙に興味がある子どもなら「月と火星、どっちに行ってみたい?」「宇宙飛行士になったら何をしてみたい?」と会話を広げてみる。
料理が好きな子どもなら「その料理を上手に作るコツは?」「次は何を作りたいの?」と興味を示すことで、子どもは自分の「好き」を認めてもらえたという安心感を得られます。
たとえ親自身が興味のない分野でも、子どもの目線に立って「なるほど、そういうところが面白いんだね」と理解しようとする姿勢が大切です。
「好き」を否定しない姿勢
親が子どもの「好き」を否定すると、創造性や情熱の芽を摘んでしまうことになりかねません。特に気をつけたいのは以下のような言葉です。
- 「将来、役に立たないからやめておいたら?」
- 親自身が、自分が好きで追及したことが、職業として成り立たなかった経験をした場合、このような発言が出るかもしれません。しかし、変化の激しい現代では、一見実用的でないように見える「好き」が、将来思わぬ形で活きることもあります。
例えば、マンガを描くのが好きだった子どもが、デザイナーやパタンナーとして活躍するケースも少なくありません。 - 「文系より、待遇がよい理系に進んだら?」
- このような偏った価値観を押し付けることは避けましょう。どの分野にも独自の価値があり、社会貢献の形は多様です。文系・理系という区分自体も、今後の社会では意味が薄れていくかもしれません。
- 「そんなことばかりやっていないで、もっと勉強しなさい」
- 時代の変化とともに、教育観もかつての「勉強第一」から、「個性を活かす」「多様な能力を育む」という方向へと変化しています。
「好き」を追求することと学校の勉強は、対立するものではありません。むしろ、興味があることを深く学ぶ過程で、読解力、調査能力、論理的思考など、学校でも役立つスキルが自然と身についていきます。
あるいは、「好き」を伸ばす過程で勉強が必要だと気づき、自発的に勉強に取り組み始めることがあるかもしれません。
子どもが何かに熱中することは、自発的な学びの貴重な機会なのです。
子どものペースを尊重する

子どもは大人とは異なるペースで成長します。「好き」の探求も同様です。すぐに成果を求めたり、大人の期待に応えるよう急かしたりするのではなく、子どものペースを尊重することが重要です。
例えば、ピアノを始めた子どもがなかなか上達しなくても、「毎日30分は練習しなさい」のように強制するのではなく、「今日はどんな曲に挑戦したい?」と自主性を引き出す声かけをしてみましょう。
例えば、ピアノを始めた子どもがなかなか上達しなくても、「毎日30分は練習しなさい」のように強制するのではなく、「今日はどんな曲に挑戦したい?」と自主性を引き出す声かけをしてみましょう。
また、子どもが「好き」を追求する過程では、一時的に熱中したかと思えば突然興味が薄れることもあります。これは自然なプロセスの一部。子どもの興味の変化を柔軟に受け止め、新たな「好き」にも同じように寄り添う姿勢を持ちましょう。
適切な距離感を保つ
子どもの「好き」を応援する上で、親がどこまで関わるべきか、その距離感は難しい問題です。過干渉になれば子どもの主体性が失われ、放任すれば孤独な挑戦になってしまいます。
適切な距離感を保つためのポイントは、「子どもが主役であること」を常に意識すること。例えば、子どもが何か困難に直面したとき、すぐに解決策を提示するのではなく、「どうすればできると思う?」と問いかけ、子ども自身が考える機会を作りましょう。また、失敗しても「次はどうしてみたい?」と前向きな視点を促すことが大切です。
適切な距離感を保つためのポイントは、「子どもが主役であること」を常に意識すること。例えば、子どもが何か困難に直面したとき、すぐに解決策を提示するのではなく、「どうすればできると思う?」と問いかけ、子ども自身が考える機会を作りましょう。また、失敗しても「次はどうしてみたい?」と前向きな視点を促すことが大切です。
5「好き」を育てて、子どもの未来をつくろう

親世代はキャリア教育と聞くと、つい「将来の職業選択」を思い浮かべがちです。
しかし本当のキャリア教育とは、特定の仕事を決めることではなく、子どもが自らの可能性を発見し、それを将来に活かす力を育むことといえます。その核となるのが、「好き」という小さな種なのです。
「好き」が必ずしも仕事になるとは限りません。サッカーが好きな子どもが全員プロの選手になれるわけでも、お絵描きが好きな子が全員イラストレーターになれるわけでもありません。しかし、「好き」に熱中したことで培われた観察力、集中力、創造性、問題解決能力は、さまざまな職業において貴重な財産となるはずです。
どんな職業を選んでも、自分の「好き」を形にしていくプロセスそのものが、充実した人生につながるともいえます。「好き」を追求する中で経験する喜びや挫折、発見や成長は、かけがえのない人生の糧となります。
また、親自身も「好き」を大切にする姿勢を忘れないでほしいと思います。料理教室に通ったり、アイドルのコンサートに行ったり、趣味の時間を楽しむ親の姿は、子どもにとって最高のお手本。
「大人になっても、『好き』を大切にすることはこんなに楽しいんだよ」というメッセージを、日々の生活の中で伝えていきましょう。
子どもの「好き」を育むことは、親子で共に成長する素晴らしい機会です。その小さな種が、やがて予測困難な時代を生き抜く強さと、自分らしく輝く喜びをもたらしてくれるでしょう。
しかし本当のキャリア教育とは、特定の仕事を決めることではなく、子どもが自らの可能性を発見し、それを将来に活かす力を育むことといえます。その核となるのが、「好き」という小さな種なのです。
「好き」が必ずしも仕事になるとは限りません。サッカーが好きな子どもが全員プロの選手になれるわけでも、お絵描きが好きな子が全員イラストレーターになれるわけでもありません。しかし、「好き」に熱中したことで培われた観察力、集中力、創造性、問題解決能力は、さまざまな職業において貴重な財産となるはずです。
どんな職業を選んでも、自分の「好き」を形にしていくプロセスそのものが、充実した人生につながるともいえます。「好き」を追求する中で経験する喜びや挫折、発見や成長は、かけがえのない人生の糧となります。
また、親自身も「好き」を大切にする姿勢を忘れないでほしいと思います。料理教室に通ったり、アイドルのコンサートに行ったり、趣味の時間を楽しむ親の姿は、子どもにとって最高のお手本。
「大人になっても、『好き』を大切にすることはこんなに楽しいんだよ」というメッセージを、日々の生活の中で伝えていきましょう。
子どもの「好き」を育むことは、親子で共に成長する素晴らしい機会です。その小さな種が、やがて予測困難な時代を生き抜く強さと、自分らしく輝く喜びをもたらしてくれるでしょう。
