column ココロの特集
子どものスマホ・SNSは大丈夫?デジタル時代に親子で守りたい心と体のルール

- 要約
- デジタル機器が子どもの日常に与える影響はメリットとデメリットの両面がある 正しいルールづくりと親子の対話が、子どもの心身の健康を守るカギ 親子で上手にデジタル機器と付き合うポイントや、よくある質問にも対応
今や、大人だけでなく子どもの日常にもすっかり定着したスマートフォンやタブレット。勉強や友人とのコミュニケーション、趣味やリラックスの場面など、デジタル機器は子どもの可能性を大きく広げてくれます。
一方で、「夜ふかしによる睡眠不足が心配」「視力への影響は?」「SNSでトラブルに巻き込まれないか」など、不安や心配が尽きないのも親心です。
とりわけ、「デジタル機器が心や発達にどんな影響を与えるか」は、多くのご家庭にとっての関心事でしょう。この記事では、親子でできるデジタル機器との上手な付き合い方や、子どものこころを守るためのポイントを、具体的なヒントとともにお伝えします。
一方で、「夜ふかしによる睡眠不足が心配」「視力への影響は?」「SNSでトラブルに巻き込まれないか」など、不安や心配が尽きないのも親心です。
とりわけ、「デジタル機器が心や発達にどんな影響を与えるか」は、多くのご家庭にとっての関心事でしょう。この記事では、親子でできるデジタル機器との上手な付き合い方や、子どものこころを守るためのポイントを、具体的なヒントとともにお伝えします。
監修:正木大貴[博士(医学)]
もくじ
1デジタル機器は子どもの心と体にどんな影響を与える?

- 要点まとめ
- メリットだけでなくリスクも。子どもの心身の発達や生活リズムに注意が必要 主な影響は「身体的」「精神的」「人間関係」「自己評価」の4つ
現代の子どもたちにとって、スマホやタブレットはごく身近な存在となっています。小学生のうちからインターネットに自然と親しみ、学校や家庭、友人との関わりの中でも“デジタル”が当たり前のものになっています。
こうした環境の変化を受け、親が「いつ、どんなふうに使えばいいの?」「デジタル機器を使う時は、どんなことに気をつけたらいいの?」と考える機会も増えてきたのではないでしょうか。
ここでは、デジタル機器の利用によって子どもたちの心や体にどのような影響があるのか、整理してみましょう。
こうした環境の変化を受け、親が「いつ、どんなふうに使えばいいの?」「デジタル機器を使う時は、どんなことに気をつけたらいいの?」と考える機会も増えてきたのではないでしょうか。
ここでは、デジタル機器の利用によって子どもたちの心や体にどのような影響があるのか、整理してみましょう。
| 影響 | メリット例 | デメリット・リスク例 |
|---|---|---|
| 身体的な変化 | 特になし | 視力低下、ドライアイ、姿勢の悪化、運動不足 |
| 精神的な変化 | 新しい発見や興奮、好奇心が高まる | 集中力や意欲の低下、睡眠障害 |
| 人間関係 | 友だちとの交流が広がる | SNSでのトラブル、親子の会話が減る |
| 自己評価 | 自己表現や情報発信の場、コミュニティとのつながり、自分の強み・特徴の確認 | 自信喪失、自己否定、他人との比較によるストレス |
| 情報リテラシー | 情報収集が早くなる、ICT学習が進む、新しい知識やネットワークが得られる | 誤った情報、フェイクニュース、個人情報の流出、誹謗(ひぼう)中傷 |
(1)デジタル機器を利用する際に注意したいことは?
デジタル機器の利用は「多くの情報にアクセスでき、知識の幅が広がる」「コミュニケーションの幅が広がる」などのメリットがある一方、長時間の利用や使い方によって、子ども心身のバランスや生活リズムの乱れにつながったりするリスクもあります。ここでは、小学生がデジタル機器を使用する際に注意したいことを挙げています。
①身体面への影響
視力低下やドライアイ
長時間のデジタル機器使用による眼精疲労や近視の進行が問題になっています。特に、スマホやタブレットを近い距離で見続けると、目のピント合わせを行う筋肉(毛様体筋)が酷使され、疲れやすくなったり、一時的にピントが合いにくくなったりすることがあります。また、画面を注視することでまばたきの回数が減少し、涙の蒸発が進みやすくなるため、結果としてドライアイや目の乾き、かすみ目を訴える子どもが多くなっています。
姿勢の崩れや運動不足
デジタル機器を手にしていると、無意識のうちに前のめりの姿勢や寝転んでの利用が増えます。こうした姿勢が慢性化すると、背骨や首への負担が高まるだけでなく、外遊びやスポーツの時間が減り、基礎的な体力や筋力の低下につながる恐れもあります。
②精神面への影響
スマホの過度な使用により、脳の報酬系(※)が頻繁に活性化されることが報告されています。例えばメールやSNSの通知がくるとすぐに反応したり、ショート動画などで刺激的な動画を見たりする刺激に脳が慣れると、普通のことでは満足できなくなったり、集中力やモチベーションの維持が難しくなったりする恐れがあります。
また、脳が疲労すると手近な快楽に流れやすくなるため、スマホの使用時間が長くなり、依存度が高まる悪循環に陥ることも指摘されています。
脳は強い刺激に慣れると、小さな出来事でイライラしやすくなったり、集中力や我慢する力が弱まったりする傾向があると言われています。また、夜遅くまでインターネットにめり込むあまりに睡眠時間が削られ、そのため寝不足になり翌日の心身の機能に影響する恐れがあります。
また、脳が疲労すると手近な快楽に流れやすくなるため、スマホの使用時間が長くなり、依存度が高まる悪循環に陥ることも指摘されています。
脳は強い刺激に慣れると、小さな出来事でイライラしやすくなったり、集中力や我慢する力が弱まったりする傾向があると言われています。また、夜遅くまでインターネットにめり込むあまりに睡眠時間が削られ、そのため寝不足になり翌日の心身の機能に影響する恐れがあります。
(※)人間の脳が「嬉しい」「楽しい」などを感じる時に活性化する、動機づけや快感に関わる神経回路。脳内で「ドーパミン」という神経伝達物質が分泌されることで、満足感や充実感が得られる。この仕組みにより「またやりたい」「もっと続けたい」という気持ちが生まれる。
③SNSやゲームでの人間関係のトラブル
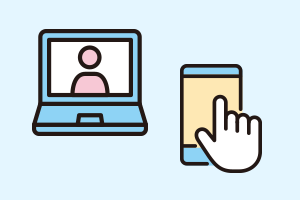
文字をメインにコミュニケーションを行うSNSでは、相手の表情やしぐさ、声の様子などが見えない分、言葉の受け取り方の違いでトラブルが起こることもあり得ます。またオンラインゲームで初めて知り合った相手とのコミュニケーション不足など、リアルとは違った「ネット特有の人間関係ストレス」を子どもも経験します。
また、ゲームやSNSの利用が生活の中心になってしまい、勉強や家族との会話がおろそかになる状態にも注意が必要です。
また、ゲームやSNSの利用が生活の中心になってしまい、勉強や家族との会話がおろそかになる状態にも注意が必要です。
④自己評価の揺れ
友達や有名人の投稿と自分を比べてしまう環境は、自己評価にも大きく影響します。特に思春期では、SNS上での「いいね」やフォロワー数などの数値的な評価が、自己価値の基準になりがちで、自己評価が不安定になるリスクが指摘されています。こうした心の揺れは、発達段階にある子どもにとって特にデリケートな問題です。
このように、デジタル機器には便利さもあれば、子どもの心身にさまざまな影響を与えるリスクもあります。大切なのは、“使い方・過ごし方”に目を向け、親子一緒によりよい付き合い方を考えていくことです。
このように、デジタル機器には便利さもあれば、子どもの心身にさまざまな影響を与えるリスクもあります。大切なのは、“使い方・過ごし方”に目を向け、親子一緒によりよい付き合い方を考えていくことです。
2家庭でできる!デジタル機器との健康的な付き合い方は?

- 要点まとめ
- 一方的な禁止より、家族で納得のできる楽しいルールづくりを 定期的なルール見直しと、楽しいオフライン体験の工夫が大切
デジタル機器が身近な存在となった今、子どもたちの心や生活を守るためには、単に「使いすぎないように気をつける」だけでは十分とは言えません。ネットやゲームにいつでも手の届く環境だからこそ、親子で納得のできるルールづくりや、心の健康を保つための工夫がますます必要になっています。
大事なのは、「親が一方的に制限する時代」から、「親子で一緒に話し合い、互いに歩み寄る時代」へ変わってきているということです。
子どもの心がすこやかに育つためには、ルールを決める過程そのものが、親子の信頼関係や安心感を生み出す大切な機会にもなります。
親子の対話を大切にしながら、家庭ごとの工夫でデジタルと心地よく付き合い、子どもの心を守っていきましょう。
ここからは、実際に家庭でできるルール作りのヒントをご紹介します。
大事なのは、「親が一方的に制限する時代」から、「親子で一緒に話し合い、互いに歩み寄る時代」へ変わってきているということです。
子どもの心がすこやかに育つためには、ルールを決める過程そのものが、親子の信頼関係や安心感を生み出す大切な機会にもなります。
親子の対話を大切にしながら、家庭ごとの工夫でデジタルと心地よく付き合い、子どもの心を守っていきましょう。
ここからは、実際に家庭でできるルール作りのヒントをご紹介します。
作成ポイント例
- 発達や年齢段階に応じて内容や使う時間を調整
- ルールは必ず親子で相談して決める
- 家族みんなが守る「デジタル宣言」を作ってもOK
(1) 子どもと一緒に「デジタル機器の使用ルール」を作る
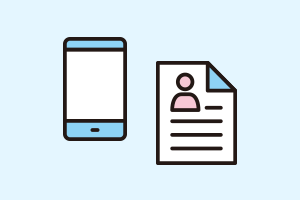
親からの一方的な制限や禁止では、子どもは反発したり隠れて使うようになったりしがちです。大切なのは、親子で話し合い、「なぜそのルールが必要か」を一緒に考え、みんなが納得のできるルールを作ることです。
家族で納得したルールは守りやすくなり、親子が互いの気持ちに寄り添うことで、安心感や信頼関係も深まります。例えば、家庭の方針や子どもの性質などに合わせて「頑張れたらボーナス(例:お手伝いでゲームやSNS使用の延長OKなど)」などの独自ルールを設けるのもよいでしょう。
家族で納得したルールは守りやすくなり、親子が互いの気持ちに寄り添うことで、安心感や信頼関係も深まります。例えば、家庭の方針や子どもの性質などに合わせて「頑張れたらボーナス(例:お手伝いでゲームやSNS使用の延長OKなど)」などの独自ルールを設けるのもよいでしょう。
年齢や発達段階に応じたルールにする
低学年のうちは親がしっかり管理し、必要な時は一緒に使うくらいの意識で問題ありません。中・高学年になったら、子どもの自主性や責任感を育てるためにも「どう使うといいと思う?」と問いかけ、話し合いながらルールを決めていきましょう。
子どもが楽しんでいることに興味をもってみる
ゲームやSNSに対し、親も「どんなゲームなの?」「SNSって、どんなところが面白いの?」など興味を持ち、場合によっては一緒に体験する意識を持ち、子どもが面白がっている世界をのぞいてみるとよいでしょう。
(2)ルールを破ってしまったらどうするかを、あらかじめ決めておく
ルールを守れなかった時のペナルティについても、ルールを決める時に考えておくことが望ましいです。守ることができない約束には意味がなく、守れないまま放置することは最も望ましくありません。
例えば、ペナルティとして「3日間のデジタル機器利用禁止」などを取り入れるのもよいです。
例えば、ペナルティとして「3日間のデジタル機器利用禁止」などを取り入れるのもよいです。
(3)「我が家のデジタル宣言」を作る
親子で話し合ったルールや決まりごとを、家族みんなで“宣言”という形にまとめてみましょう。紙に書いてリビングに貼ったり、その紙に子どもがイラストや飾り付けをして楽しく仕上げたりすると、「自分たちで決めた」という自覚が生まれ、守りやすくなります。
デジタル宣言例
- ゲームや動画は●時までに終わらせます。
- 食事中、寝る1時間前はスマホ・タブレットを使いません。
- ネットで嫌なことがあったら家族にすぐ相談します。
- ゲームや動画視聴は1日●時間までとし、1日30分以上は体を動かします。
- 休日は家族みんなでオフラインタイムを作ります。
- 親もスマホ利用に気をつけて、長時間になった時は理由を伝えます。
- ルールは定期的に話し合って見直します。
- Q.ルール違反があったらどうする?
- A.なぜ守れなかったかを話し合い次に活かす
頑張った時は「ボーナス」やご褒美、違反時は適度なペナルティでバランスを
(4) デジタルデトックスも意識しよう
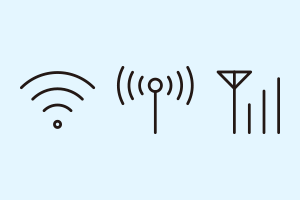
デジタル機器から“意識的に離れる”時間(デジタルデトックス)を作るのも心身のリセットにつながります。家族みんなで外出したり、体を動かしたり、ボードゲームや料理などのオフラインの楽しみを増やしたりすることは、親子でリラックスし合える大切な時間になります。
デジタルデトックスを続けるコツは、親が率先して声をかけたり、一緒にオフラインタイムを決めたりすることです。
デジタルデトックスを続けるコツは、親が率先して声をかけたり、一緒にオフラインタイムを決めたりすることです。
(5) 親自身もデジタルとの関わり方を意識する
忙しい毎日の中で、つい親もスマホやネットに夢中になってしまい、気づけば家族との会話が減っていた……ということはありませんか?「最新情報を集めなきゃ」「子育てに失敗しないように」と頑張りすぎて、親自身が疲れてしまうこともあります。
そんな時こそ、「自分もデジタルデトックスしてみよう」と意識してみてください。親が自分の時間を大切にし、子どもとちゃんと向き合うことで、子どもにも安心感を与えられます。
また、「親も子どもも、ともに成長の途中」という気持ちで、無理せず自分の心も大切にすること。「親だから完璧にできなきゃ」と頑張りすぎる必要はありません。親が自分の心を大切にすることも、子どもの心を守るために必要です。
そんな時こそ、「自分もデジタルデトックスしてみよう」と意識してみてください。親が自分の時間を大切にし、子どもとちゃんと向き合うことで、子どもにも安心感を与えられます。
また、「親も子どもも、ともに成長の途中」という気持ちで、無理せず自分の心も大切にすること。「親だから完璧にできなきゃ」と頑張りすぎる必要はありません。親が自分の心を大切にすることも、子どもの心を守るために必要です。
3デジタル機器について子どもと話す時、コミュニケーションのヒントは?

- 要点まとめ
- デジタル機器を題材に楽しかったこと・トラブルなど気軽に話しやすい雰囲気づくりを 子どもが何でも話せる「安心感」をもてるような声かけが大事
デジタル機器が身近な現代では、子どもたちの毎日の出来事や感じたことも、ますます多様になっています。思いがけず嬉しい発見をしたり、時には不安や困りごとに出会ったりすることもあるでしょう。
こうした日々の体験について親子で言葉を交わすことは、悩みや気持ちを一人で抱え込まずに済む安心感につながり、子どものこころの安定や親子の信頼関係を育てる大切な土台となります。
とはいえ、「実際にはどう話しかければいいか分からない」「どんな話題なら子どもが心を開いてくれるのだろう」と悩むこともあるのではないでしょうか。
そこでここでは、デジタル機器をきっかけにした日常の中で、親子のこころが近づく会話のヒントや具体例をご紹介します。
こうした日々の体験について親子で言葉を交わすことは、悩みや気持ちを一人で抱え込まずに済む安心感につながり、子どものこころの安定や親子の信頼関係を育てる大切な土台となります。
とはいえ、「実際にはどう話しかければいいか分からない」「どんな話題なら子どもが心を開いてくれるのだろう」と悩むこともあるのではないでしょうか。
そこでここでは、デジタル機器をきっかけにした日常の中で、親子のこころが近づく会話のヒントや具体例をご紹介します。
シーン別の対話例
楽しかった経験を聞き出したい時
- 「今日の動画、どこが面白かった?」
- 「どんな新しいことを知った?」
動画やゲームで楽しい思いをした時には、子どもの気持ちに寄り添いながら、「今日見た動画、どんなところが面白かった?」「新しく知ったことや、びっくりしたことはあった?」など、感想や発見を尋ねてみましょう。
「好きなキャラクター、どこが好きになったの?」と具体的に聞いてみるのもおすすめです。親が関心をもって共感することで、子どもは自分の世界を安心して話しやすくなります。
「好きなキャラクター、どこが好きになったの?」と具体的に聞いてみるのもおすすめです。親が関心をもって共感することで、子どもは自分の世界を安心して話しやすくなります。
嫌なこと・困ったことがないか聞きたい時
- 「ネットで困ったことはある?」
- 「もし嫌なメッセージがきたらどうする?」
「最近、ゲームやネットで困ったことあった?」「もし誰かから意地悪なメッセージが来たら、どうする?」など、子どもがトラブルを経験した時も想定して、日頃から自然に声をかけてみましょう。また、「友達とゲームやSNSを使った時、嫌な気持ちになったことはある?」と聞くことで、悩みや不安を表現しやすくなります。
この時、「どんなことでも、あなたが『なんだか嫌だな』と感じることがあったら、必ず教えてね」と伝え、安心して何でも打ち明けられる空気を大切にしてください。
この時、「どんなことでも、あなたが『なんだか嫌だな』と感じることがあったら、必ず教えてね」と伝え、安心して何でも打ち明けられる空気を大切にしてください。
ルールや約束を守れなかった時
- 「どうして長く使っちゃったの?」
- 「寝る前にスマホしてたけど、ちゃんと寝られたの?」
デジタル機器の使い方や時間について話す時は、「最近、スマホを使う時間が長くなってきたみたいだけど、何か理由があるのかな?」「寝る前に使うと、朝起きるのが大変じゃない?」など、子どもの様子に寄り添いながら一緒に考える対話を心がけましょう。
ただ決まりを守らせるのではなく、子どもの意見にも耳を傾けて、「どうしたら、ルールを守って(デジタル機器を)使えると思う?」「ルールを守るのが難しいなら、もう一度、みんなでルールについて話し合ってみようか」など、一緒に工夫していく気持ちが、親子間での信頼や安心につながります。
デジタル機器をめぐる小さなやりとりが、子どもが安心して成長できる土台となり、心のケアにもつながっていきます。
ただ決まりを守らせるのではなく、子どもの意見にも耳を傾けて、「どうしたら、ルールを守って(デジタル機器を)使えると思う?」「ルールを守るのが難しいなら、もう一度、みんなでルールについて話し合ってみようか」など、一緒に工夫していく気持ちが、親子間での信頼や安心につながります。
デジタル機器をめぐる小さなやりとりが、子どもが安心して成長できる土台となり、心のケアにもつながっていきます。
4【まとめ】親子で一緒に考える「デジタル世代」とは?
- 要点まとめ
- デジタル社会で子どもを守るコツは「親子で話し合い、納得し、柔軟に工夫すること」 困った時は学校や専門家の力も借りてOK 完璧を目指しすぎず、家族オリジナルのやり方で前向きにチャレンジ!

デジタル社会は絶えず姿を変え、子どもたちの毎日にも新しいチャレンジが次々と訪れます。そんな中で、親が一方的に教えたり制限したりするだけではなく、親子で一緒に悩み、話し合い、納得のできるルールや工夫を見つけていくことが、これからの時代にますます大切になっていきます。
日々の出来事や気持ちをできるだけ言葉にして共有すること、家庭ごとに無理のない方法でお互いの心に寄り添う時間を意識すること。それが子どもの安心感や自信につながり、家庭に支え合いの輪が生まれます。
時には、「正解がわからない」「どう付き合うべきか迷う」と感じることがあるかもしれません。でも、家族のかたちは一つひとつ違うのが当然です。親も子どもも、デジタル時代を生きる学びのプロセスを一緒に歩んでいるのだと考えてみてください。
不安や悩みを親が一人で抱え込む必要はありません。学校や地域の相談窓口、専門家など信頼できる外部のサポートも、もしもの時の選択肢として考えておきましょう。
大切なのは、親子がこれからも対話を続けながら、柔軟に、前向きに変化を受け入れていくこと。「一人じゃない」「わかりあおうとしている」――そんな実感こそが、子どもにとっても大人にとっても、デジタル時代を安心して歩むための支えになるはずです。
日々の出来事や気持ちをできるだけ言葉にして共有すること、家庭ごとに無理のない方法でお互いの心に寄り添う時間を意識すること。それが子どもの安心感や自信につながり、家庭に支え合いの輪が生まれます。
時には、「正解がわからない」「どう付き合うべきか迷う」と感じることがあるかもしれません。でも、家族のかたちは一つひとつ違うのが当然です。親も子どもも、デジタル時代を生きる学びのプロセスを一緒に歩んでいるのだと考えてみてください。
不安や悩みを親が一人で抱え込む必要はありません。学校や地域の相談窓口、専門家など信頼できる外部のサポートも、もしもの時の選択肢として考えておきましょう。
大切なのは、親子がこれからも対話を続けながら、柔軟に、前向きに変化を受け入れていくこと。「一人じゃない」「わかりあおうとしている」――そんな実感こそが、子どもにとっても大人にとっても、デジタル時代を安心して歩むための支えになるはずです。
- 【参考リンク・資料】
- 集中力や記憶力が落ちていませんか?「スマホ脳疲労」に注意/大正製薬
- “スマホ脳疲労”記憶力や意欲が低下!?/NHK「クローズアップ現代」
