column ココロの特集
小学生とAI──親が知っておきたい、子どものココロへの影響と付き合い方

- 要約
- AIのメリットとリスクを正しく理解することが重要 AIの答えを「正しい・間違い」と単純に判断せず、親子で感じ方や考え方を話し合うことが大切 AIを“頼れる相棒”として上手に活用していく姿勢が、今後さらに大切になる
「今日、学校でAIを使って勉強する授業があったよ」。最近、小学生たちからこんな声が聞かれるようになっています。AI(ChatGPTやスマートスピーカーなど)は、家庭や学校の“当たり前”の風景になりつつあります。
文部科学省も2024年7月、「AI活用」に関するガイドライン」を発表しました。最新の技術を子どもたちの未来に役立てたい……そう願う社会の動きが加速する一方で、「AIを使うことで子どもの心はどう変わる?」「親としてどんな付き合い方がいいの?」など、不安や疑問を感じている保護者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では「小学生とAI」をテーマに、AI時代を生きる子どもの心への影響や、親子でできるコミュニケーションや、AIとのよりよい付き合い方について考えました。
文部科学省も2024年7月、「AI活用」に関するガイドライン」を発表しました。最新の技術を子どもたちの未来に役立てたい……そう願う社会の動きが加速する一方で、「AIを使うことで子どもの心はどう変わる?」「親としてどんな付き合い方がいいの?」など、不安や疑問を感じている保護者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では「小学生とAI」をテーマに、AI時代を生きる子どもの心への影響や、親子でできるコミュニケーションや、AIとのよりよい付き合い方について考えました。
監修:正木大貴[博士(医学)]
もくじ
1小学生とAIの関わりで「心」はどう変わる?

- 要点まとめ
- AIは子どもの「わかった!」「すごい!」といった自信や達成感を引き出す効果がある。 一方で、考える力や粘り強さの低下、現実逃避や依存など、心への悪影響の可能性もある。 AIのメリットとリスクを正しく理解することが重要。 AIを「道具」として賢く使いこなす力が、これからの時代に求められる。
1小学生がAIとやり取りして感じる自信と依存リスク
「わからないことがあったら、まずAIに聞いてみる」――日常生活の中に、そんな場面が増えてきているのではないでしょうか。
AIは私たちの質問に即座に答えてくれるため、「わかった!」「なるほど!」といった喜びや、「新しい知識を得た」「前より賢くなったかも」という自己効力感(「自分ならできる」という自信)にもつながります。一方で、「確かに便利だけれど、『なんでもAIに頼ればいい』と考えやすくなり、自分自身で考え抜いたり、物事に粘り強く取り組んだりする力が育ちにくくなるのでは……」と心配する声もあります。
ですが、使い方によってはAIが新しい視点に基づいた問いを提示してきて視野が広がったり、子どもの「なぜ?」を掘り下げたりすることにつながり、「もっと知りたい」「次はこんなことも調べよう」と、子どもの好奇心が刺激されるケースもあり得ます。つまり、AIとのやり取りは、その使い方によって子どもの成長を大きく後押しする場合もあれば、逆に自分で粘り強く考える力を弱めてしまう恐れもあります。
また、悩み相談でAIを用いると、「すごいですね!」「頑張って!」のような誉め言葉や前向きな言葉、励ましなどをくれることが多いですが、これは人間が実際にその子を見て感じた評価と同じとはかぎりません。感情を持たないAIが投げかける言葉と、周囲の大人や友だちが向けてくれる言葉とは、意味合いや受け止め方に違いがあります。
さらに、AIはちょっとした愚痴や悩みの“聞き役”として使いやすいというメリットがあります。自分の意思や感情がある人間を相手に、延々と愚痴や悩みを聞かせると迷惑をかけてしまいますが、感情を持たないAIなら気軽で安心できるといった一面もあるでしょう。
しかし、そうした気楽さから「いつでも助けてくれる存在」という感覚が強くなるほど、AIに頼りがちになる恐れがあります。AIから得られる共感や肯定の言葉だけに安心してしまうと、次第に人との関わりよりもAIを優先する、“AI依存”のリスクが生じる可能性も否定できません。AIは便利な道具であり、人の代わりではないことを忘れず、適度な距離感を保つことを意識しましょう。
AIは私たちの質問に即座に答えてくれるため、「わかった!」「なるほど!」といった喜びや、「新しい知識を得た」「前より賢くなったかも」という自己効力感(「自分ならできる」という自信)にもつながります。一方で、「確かに便利だけれど、『なんでもAIに頼ればいい』と考えやすくなり、自分自身で考え抜いたり、物事に粘り強く取り組んだりする力が育ちにくくなるのでは……」と心配する声もあります。
ですが、使い方によってはAIが新しい視点に基づいた問いを提示してきて視野が広がったり、子どもの「なぜ?」を掘り下げたりすることにつながり、「もっと知りたい」「次はこんなことも調べよう」と、子どもの好奇心が刺激されるケースもあり得ます。つまり、AIとのやり取りは、その使い方によって子どもの成長を大きく後押しする場合もあれば、逆に自分で粘り強く考える力を弱めてしまう恐れもあります。
また、悩み相談でAIを用いると、「すごいですね!」「頑張って!」のような誉め言葉や前向きな言葉、励ましなどをくれることが多いですが、これは人間が実際にその子を見て感じた評価と同じとはかぎりません。感情を持たないAIが投げかける言葉と、周囲の大人や友だちが向けてくれる言葉とは、意味合いや受け止め方に違いがあります。
さらに、AIはちょっとした愚痴や悩みの“聞き役”として使いやすいというメリットがあります。自分の意思や感情がある人間を相手に、延々と愚痴や悩みを聞かせると迷惑をかけてしまいますが、感情を持たないAIなら気軽で安心できるといった一面もあるでしょう。
しかし、そうした気楽さから「いつでも助けてくれる存在」という感覚が強くなるほど、AIに頼りがちになる恐れがあります。AIから得られる共感や肯定の言葉だけに安心してしまうと、次第に人との関わりよりもAIを優先する、“AI依存”のリスクが生じる可能性も否定できません。AIは便利な道具であり、人の代わりではないことを忘れず、適度な距離感を保つことを意識しましょう。
2AIを使うことによる満足感の落とし穴

AIと会話したり答えをもらったりすることで、子どもは一時的な満足感を得ることができます。AIはいつでも、どこでも、優しく、ときには面白く対応してくれます。しかしその一方で、リアルな友だちや家族とじっくり話す時間、直接やり取りする意欲が減ってしまうリスクも指摘されています。
また「友だちとけんかをしてしまった」「いじめられている」などの悩みを抱える子どもが、親や先生、友だちなどには打ち明けづらいと感じて、AIに相談することもあるでしょう。人と話すのが苦手なときや、AIになら言いやすい内容もあるかもしれません。しかし「AIならではの安全な距離感」は、時には子どもの心の拠りどころになることがある一方で、AIに頼りきりになってしまうなど、のめり込むリスクもあります。
実際、PR記事をメディア・消費者に効率的に届けるオンラインサービス「PR TIMES」が2023年に行った「小学生のAI利用実態に関する調査」では、「保護者の半数以上が『AIが友だちや家族とのコミュニケーション時間を減らすのではないか』と危惧している」と発表されています。
特に感受性が強かったり、一人で抱え込む傾向があったりする子どもは、AIならではの気軽さに頼り過ぎてしまうことも。「AIは万能ではない」「困ったら必ず周囲の大人に相談する」という基本方針を、家庭で何度も伝えていくことが欠かせません。また、自分の世界がAIだけで完結し、現実の友だちや家族との関係が薄まってしまうリスクを見落とさないようにしましょう。
また「友だちとけんかをしてしまった」「いじめられている」などの悩みを抱える子どもが、親や先生、友だちなどには打ち明けづらいと感じて、AIに相談することもあるでしょう。人と話すのが苦手なときや、AIになら言いやすい内容もあるかもしれません。しかし「AIならではの安全な距離感」は、時には子どもの心の拠りどころになることがある一方で、AIに頼りきりになってしまうなど、のめり込むリスクもあります。
実際、PR記事をメディア・消費者に効率的に届けるオンラインサービス「PR TIMES」が2023年に行った「小学生のAI利用実態に関する調査」では、「保護者の半数以上が『AIが友だちや家族とのコミュニケーション時間を減らすのではないか』と危惧している」と発表されています。
特に感受性が強かったり、一人で抱え込む傾向があったりする子どもは、AIならではの気軽さに頼り過ぎてしまうことも。「AIは万能ではない」「困ったら必ず周囲の大人に相談する」という基本方針を、家庭で何度も伝えていくことが欠かせません。また、自分の世界がAIだけで完結し、現実の友だちや家族との関係が薄まってしまうリスクを見落とさないようにしましょう。
2AIとのふれあいが、新しい「対人関係」を生む?
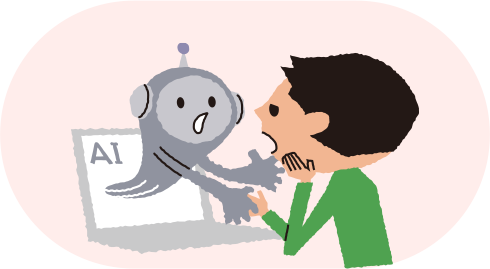
- 要点まとめ
- 子どもがAIを「友だち」や「相談相手」と感じるケースが増えている AIに過度に頼ると、人間関係に必要な“ズレ”や“もどかしさ”を経験する機会が減る恐れがある AIとの関わりと人間同士のつながりの違いを理解しておくことが重要

AIが身近な存在となるにしたがって、なかには「AIが友だちの代わり」「AIが先生役もやってくれる」「悩みはAIにしか相談できない」と考える子が出てくるかもしれません。しかし、AIとのやり取りでは人間同士特有の感情や共感、ちょっとした“ズレ”や誤解、“もどかしさ”を感じにくくなります。
もちろん、AIが共感しているように答えを返してくることはありますが、その反応は蓄積されたデータやパターンに基づくものに過ぎません。たとえば相手が傷つく姿を見てショックを受ける、自分が誰かを傷つけてしまったと反省するといった経験を、AIとの関わりでは味わいにくいのです。
たしかに、AIとやり取りしていると「本音をぶつけても誰も傷つかない」「自分も嫌な思いをしなくてすむ」という気になりがちです。でも、それでは生身の人間とどう接するべきかを学ぶ機会が減ってしまいます。「人間関係の煩わしさから逃げてAIだけでいい」となってしまうことが、一番のリスクといえるかもしれません。
さらにAIは、「話しやすい」「反論しない」「受け止めてくれる」といった魅力から、“一時的な心の避難所”にもなりやすいツールです。ただし、“本当に困ったときに必要なのは人間の温かさや愛情”だということ、そして、「面倒に感じること」「衝突」を避けるだけでは、他者との折り合いをつける力、自分の思いを伝えて共感してもらう喜びを経験する機会が減ってしまうことも心に留めておきましょう。
もちろん、AIが共感しているように答えを返してくることはありますが、その反応は蓄積されたデータやパターンに基づくものに過ぎません。たとえば相手が傷つく姿を見てショックを受ける、自分が誰かを傷つけてしまったと反省するといった経験を、AIとの関わりでは味わいにくいのです。
たしかに、AIとやり取りしていると「本音をぶつけても誰も傷つかない」「自分も嫌な思いをしなくてすむ」という気になりがちです。でも、それでは生身の人間とどう接するべきかを学ぶ機会が減ってしまいます。「人間関係の煩わしさから逃げてAIだけでいい」となってしまうことが、一番のリスクといえるかもしれません。
さらにAIは、「話しやすい」「反論しない」「受け止めてくれる」といった魅力から、“一時的な心の避難所”にもなりやすいツールです。ただし、“本当に困ったときに必要なのは人間の温かさや愛情”だということ、そして、「面倒に感じること」「衝突」を避けるだけでは、他者との折り合いをつける力、自分の思いを伝えて共感してもらう喜びを経験する機会が減ってしまうことも心に留めておきましょう。
子どもの個性とAI活用
たとえば、繊細で人と対面して自分の思いを話すのが得意でない子どもは、AIと話すことによって“自己表現力”の練習になることもあります。また、「AIに何でも話せるようになったことで、少しだけ自信がつき、家族や友だちにも相談できるようになった」というケースもあるでしょう。
AIの影響は一人ひとり違います。否定的に決めつけず、子どもの個性や発達に応じて使い方を工夫することも、これからの家庭や学校に大切な視点です。
AIの影響は一人ひとり違います。否定的に決めつけず、子どもの個性や発達に応じて使い方を工夫することも、これからの家庭や学校に大切な視点です。
3AI時代の親子コミュニケーションのヒントとは?
- 要点まとめ
- AIの答えを「正しい・間違い」と単純に判断せず、親子で感じ方や考え方を話し合うことが大切。 「どう感じた?」「どう考えた?」「なぜこの答えが出たのか?」といった対話を通じて理解を深める。 家族でAIの使い方やルールを話し合い、日常のコミュニケーションに活かすことが重要。
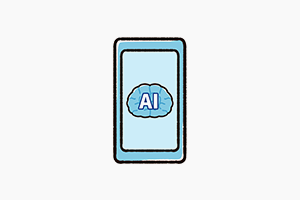
AIの答えと自分の意見が違うとき、「自分の考えは間違っているのかな?」と不安になったり、なぜ違うのか悩んでしまったりする子どももいるかもしれません。でも、大切なのはどちらが正しいか決めることではなく、「どう考えた?」「その答えを見て、どんな気持ちになった?」と、親子で対話することです。大人自身もAIを体験してみることで、「こういう返答もあるんだ」「それはちょっと違うと思うな」など、リアルな感想を子どもと共有しやすくなります。
たとえば、子どもがAIに「カブトムシの育て方」を尋ねたとします。AIが答えた後で、「どこが面白かった?」「お父さん(お母さん)はこんな育て方も知っているよ、どう思う?」などと会話を広げてみましょう。
また、家庭でAI体験をシェアする時間を作るのもおすすめです。「今日はどんな質問をAIにしてみた?」「どんな答えだった?」「そのときどんな気持ちになった?」など、気軽に話してみてはどうでしょうか。AIの使い方は、むしろ子どもの方が親より詳しいかもしれません。
たとえば、子どもがAIに「カブトムシの育て方」を尋ねたとします。AIが答えた後で、「どこが面白かった?」「お父さん(お母さん)はこんな育て方も知っているよ、どう思う?」などと会話を広げてみましょう。
また、家庭でAI体験をシェアする時間を作るのもおすすめです。「今日はどんな質問をAIにしてみた?」「どんな答えだった?」「そのときどんな気持ちになった?」など、気軽に話してみてはどうでしょうか。AIの使い方は、むしろ子どもの方が親より詳しいかもしれません。
親子の会話例
「AIはこう答えてくれたけど、お父さん(お母さん)はこんなふうに思うよ。あなたは何を感じた?」
こうした「気持ち」をシェアする時間が、AI時代ならではの親子の絆を深めるポイントになるでしょう。
こうした「気持ち」をシェアする時間が、AI時代ならではの親子の絆を深めるポイントになるでしょう。
家庭内でおすすめの工夫
- 定期的な「AI相談会」: 週に1回ほど、家族みんながAIを使ってみて印象や感想を話す場をつくる。
- 「わが家のAIルールづくり」: どんなことに使えばいいか・使わない方がいいかを一緒に考える。
- 親も積極的に体験する: たとえば「AIで晩ごはんの献立を考えてみる」「家族の予定表作りをAIと話しながら作成」する、など家庭の“便利な相棒”役としての使い方を体感してみる。
4小学生とAI・よくある疑問&親のためのアドバイス(Q&A)

- 要点まとめ
- AI依存やリアルな友人関係への影響が心配な場合のポイントをQ&A形式で整理している 子どもへの見守り方や声のかけ方の工夫を紹介 「AIは万能ではない」という認識を子どもに伝える方法を解説
- Q:AIに頼りすぎることで、リアルな友だちとうまく付き合えなくならないか、心配です。
- A:大切なのはバランスです。これからAIはさらに身近で便利な存在になっていくはずなので、使い方を理解したり、より詳しく学んだりすること自体は望ましい面もあります。また、AIとのやり取りは会話の練習や自己表現のきっかけになることもあります。もともと対人コミュニケーションが苦手な場合、AIを通じてコミュニケーションに自信をつけ、実際の友だちづくりに活かせることも考えられます。子どものその時の状態に応じて、さりげなく気持ちを受け止めてあげましょう。「AIばかり使っているから、友だちと付き合えないんじゃないの?」と決めつけないことも大切です。
- Q:一日中AIを使っている子、どう見守ればよい?
- A:まずは子どもがAIをどう使い、何を楽しんでいるのか、親も関心を持ちましょう。「何が楽しい?」「どんなことを聞いた?」など、気軽に話しかけてみるところから始めてはどうでしょうか。「ずっとAIを使っていて、何をしているの?」などと責めるより、親子で話す時間を多く持つことが、自然な子どもとAIとの距離感につながるはずです。
- Q:AIの回答はすべて信用していいの?
- A:AIの答えは必ずしもすべて正解とは限りません。ときには間違った情報や古い情報に基づく回答、勘違いした解釈を返すこともあります。「この情報は本当に正しいのかな?」と親子で一緒に調べたり、「他にどんな意見があるのかな?」と話し合ったりすることが、情報を鵜呑みにしない力につながります。「疑ってみる力」も、これからはとても大事です。小学生は知識のベースや背景事情をまだ十分に持っていない場合が多いので、「AIがこう言っていたよ。AIの方が正しいんじゃない?」と言われたときに、「それはなぜそうなると思う?」「本で調べたり、先生に質問したりしてみたら?」と、複数の角度から考えさせてみましょう。
5AIと子どもの心──これからの家庭で大切にしたいこと
- 要点まとめ
- 感情を持たないAIとの付き合い方は、家庭や子どもによって異なる 子ども自身の経験や人との関わりを大切にすることが重要 AIを“頼れる相棒”として上手に活用していく姿勢が、今後さらに大切になる
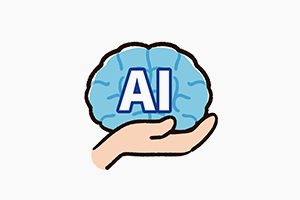
改めて意識したいのは、AIは人と完全に同じようには心を通わせることはできない存在だということです。AIは人と人、あるいは人と新しい情報をつなぐ“メディア”や“サポーター”のようなもの――。そんな発想で家庭でも付き合っていくのが、これからの時代にふさわしいでしょう。
家族や友だちとのつながりを大切にしつつ、「AIを、人間の良い協力者としてどう活用できるだろう?」と親子で話し合う時間をぜひ設けてみてください。
「AIだから…」と怖がったり排除したりせず、「人とは違うパートナー」と理解しながら、これからのAI時代を前向きに歩んでいきたいものです。
家族や友だちとのつながりを大切にしつつ、「AIを、人間の良い協力者としてどう活用できるだろう?」と親子で話し合う時間をぜひ設けてみてください。
「AIだから…」と怖がったり排除したりせず、「人とは違うパートナー」と理解しながら、これからのAI時代を前向きに歩んでいきたいものです。
これからのAIと子どもたちの未来に向けて
急速に進化するAI。これからは「AIリテラシー」(AIの理解・活用力)も子どもの学びの重要な柱になります。実際、各地の公立校では「生成系AI」を使った探究学習や、AIリテラシー教育の試みも始まっています。また、子どもがAIを活用する力は将来のキャリアや社会性にも直結しているといわれ、「AIとどう共存していくか?」という対話を家庭でも始めておくことは、子どもたちの“生きる力”を育むうえで必須になりつつあります。
大人も一緒に学ぶ姿勢を持ち続け、困ったときは迷わず相談し合える親子関係を築いていきましょう。AIが味方となるか、それとも依存の落とし穴となるか──未来を決めるのは使う「人」の側です。
この記事を、親も子どももAIと上手に付き合うための小さなヒントにしてください。
大人も一緒に学ぶ姿勢を持ち続け、困ったときは迷わず相談し合える親子関係を築いていきましょう。AIが味方となるか、それとも依存の落とし穴となるか──未来を決めるのは使う「人」の側です。
この記事を、親も子どももAIと上手に付き合うための小さなヒントにしてください。
AIに関する用語
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| AI(人工知能) | 人間のように考えたり、会話したりできるコンピューターやプログラムのこと。 |
| ChatGPT | 会話ができるAIの一つ。質問に答えたり、文章を作ったりするAIツールの名前。 |
| スマートスピーカー | 声で話しかけて使う、AIを搭載したスピーカー。質問や音楽の再生などができる。 |
| 生成AI | 新しい文章や絵、画像などを自動で作り出すAIのこと。 |
| プロンプト | AIに「これをしてほしい」とお願いする言葉や指示の文章。 |
| AIリテラシー | AIを正しく理解し、上手に使う力や知識のこと。 |
| 探究学習 | 興味・課題に合わせて自分で調べ、考え、深く学ぶ新しい学び方。 |
